2セクションは流石に長すぎる気もしたので(笑)、分量によっては1セクションのみを読み進める形にしようかと思います。
急ぐものでもないし、のんびりいかせていただきましょう。
今回は偉大なるエス小説家・吉屋信子さんについてのセクションですが、故人であり、最早歴史上の偉人ともいえるため、吉屋さんに関しては本文中では敬称略を貫かせていただきましょう。
(まぁ、歴史上の人物やスポーツ選手を呼び捨てにする風潮もどうなの、といわれがちではありますが…。)
(※追記:後に翻訳の方針を変更したので、以前の記事含め、既に志村さん他、現存する人名も全て敬称略の形に変更済みという形になっています。)

###############
That Type of Girl(そっち系のひと)
志村貴子『青い花』に関する考察
著/フランク・へッカー 訳/紺助
(翻訳第3回:13ページから19ページまで)
吉屋へのオマージュ(敬意)
イントロダクションで、『青い花』は過去の百合作品をベースにメッセージが紡がれていると書いた。これは、物語が正式に幕を開ける前から既に始まっているといえるのである:青い花第一話は『花物語』(英語タイトル『Flower Story』)と題され、これは20世紀初頭に作家・吉屋信子によって書かれたエス小説のシリーズ『花物語』(英語タイトル『Flower Tales』)に敬意を表してのオマージュといえよう(『青い花』(1) p. 4/SBF, 1:4)。
吉屋の人生および作品を理解するには、少なくとも四つのキーがある:20世紀初頭の家父長制社会に生きるレズビアンであったこと、文学の天才であったこと、比較的特権階級で裕福な子供であったこと、そして三人の兄がいる、家庭内で唯一の娘であったということである*1(※訳注:公式情報によると、兄が四人、弟が二人の七人兄弟(弟は夭折とあるため、実質六人兄弟)とあったが、兄弟の中で紅一点であったことには変わらないようである)。
吉屋の家族は中流階級に属していたため(父親は地方都市の警察署長)、吉屋本人は家族から工場や売春宿(明治の日本において、それは多くの少女にとって避けがたい運命であった)で働かせられることを免れた。代わりに、彼女は学校に通うことができ、その文学的才能を早くから教師たちに認められていた。しかし、作家として大きく期待されていたにもかかわらず、伝統的な男女の役割分担を重んじ、兄たちを贔屓する母には、疎ましがられていると感じていた。その後高校を卒業し、19歳で家を出て上京してからは、比較的自立した生活を送ることができるようになった*2。
20世紀初頭の日本社会では、そういった同性愛的物語の形式や、作家として、また女性を愛する女性として彼女が追求し得る戦略に対して一定の制限が課されていたにもかかわらず、レズビアンとして、エス関係の少女の魅力的な物語を紡ぐことにかけては、吉屋は他の誰よりも優れていた。一方で、少女向け雑誌の台頭により、欧米やキリスト教的恋愛観や個人主義の影響を受け、女子校内での同性同士の恋愛関係という考え方が人気を博すようになった。吉屋はこのトレンドの中心にいたのである。
同時に、キリスト教的道徳観と欧米の性科学者の著作にまとわる科学的オーラとにより、同性同士の関係がある範囲を超えてしまうと、「病気」や「異常」とみなされるようになっていった―例えば、1911年に世間を騒がせた元級友同士の20歳の女性二人が起こした心中事件などが挙げられよう*3。
このような事件は当時としては珍しいことではなく、吉屋が作家として名声を得、経済的成功を収めた時期には、そういった女性たちのセンセーショナルな記事が大衆紙に掲載されるのが常であった。まさに吉屋自身が書いている類の話題であるこういった物語の永続的なテーマは、女子学生の恋愛に対し危険を孕み得るという仮定のもと、吉屋は、自身の芸術作品やその他の著作、さらには自身の生活の中で、これらの問題に対処することを余儀なくされたのである。その際、彼女は時代や状況に応じて三つの戦略をとったと考えられる。
第一に、『花物語』において、吉屋は女学生の恋愛(あるいはそれに類する生徒と教師の関係)を、そもそも時間と場所が限定されており、一時的に花開きはするが、その後成人して結婚という責任を負うようになると、日本の社会規範の厳しい風雨にさらされて枯れる運命にある、と描いた。この代替案は、考えられないまではいかなくとも、少なくとも口にすることはできないものであった。
例えば、『黄薔薇』では、サッフォー(※訳注:古代ギリシャの女性詩人)の生涯と愛について生徒に語った女性教師は、少女の両親が計画する見合い結婚に反論する力を失い、代わりに即座に見合い結婚の説得に同意してしまう:「彼女は、両親が子供の結婚相手を決めるのは良くないという主張を常にひとしきり続けていた。しかし、今、この両親の前に立つと、そのどれもが説得力を失ってしまったのである。」*4。
吉屋はまた、日本の大衆を安心させるために、ノンフィクション作品の中で、女子学生の恋愛は適切であり、生徒にとって有益でさえあるという自身の主張を、イギリスの社会学者エドワード・カーペンターの文献を引き合いに出すことで裏付けるといった苦心もしていた*5。
そのカーペンターの方は、イギリスの詩人・文芸評論家であるジョン・アディントン・シモンズの影響を受けている。シモンズは、ルネサンス以降の欧米の多くの作家の伝統として、キリスト教道徳に代わるものを古典の世界に求め、1883年に『ギリシャ哲学の問題点』という無害な題名の本を自費出版した*6。シモンズは、古典ギリシャの「少年愛」―「男性と青年の間に存在し、社会によって認められ、意見によって保護される、情熱と熱意のある愛」―その最高のものは、男性的友情の気高い理想を具現化していると主張した:「恋人は教え、(愛されし者)は学んだ;そうして男から男へ、ヒロイズムの伝統は受け継がれていったのである。」*7
カーペンターはシモンズと文通を続け、1892年か1893年に、その『ギリシャ哲学の問題点』を送ってもらっていた*8。カーペンターは、1890年代に書かれ、1899年に初版が出版され、後に彼の著作『Intermediate Sex(中間の性)』に収録された『Affection in Education(教育における愛情)』というエッセイの中で、同様のモデルを現代イギリス社会、特に教育の分野に適用している*9。カーペンターは、「二人の少年、あるいは少年と教師との間の愛着を官能的なものに他ならないと決めつけることがあまりにも多すぎて、…(中略)…、世間を混乱させている」と断じた:「愛着という絆が二人の間に存在するとき、誰が少年を啓発し、彼の成長する心を導くのに適している((教師は)時に自らがそうだと感じる)だろうか?」
シモンズもカーペンターも、男性同性愛に主眼を置いており、女性同士の関係は無視するか、あるいは男性同士の関係より劣っているとしていた*10。カーペンターは、女子学生同士の関係に目を向けた際、「その大部分は、弱く感傷的な方向のあくまで友情関係であり、彼女たち自身も、 そこから導かれる習慣も、あまり健全なものではない」と記している*11。
したがって、『中間の性』の日本語訳(1914年および1919年に再版)の出版後、「日本でこの作品が女子学生の同性間関係を弁護するのに使われていたことは極めて驚きで、想定外」であったと述べられている。吉屋信子は、1921 年および1923年に発表した二つのエッセイで、「カーペンターによる女性同士の親密さにまつわるネガティブな表現は無視して、代わりに男性同士の愛着についてポジティブな議論を採用」し、年上の女性と年下の少女、あるいは女性教師と女子生徒との関係を正当化したと記している*12。
しかし、吉屋は『花物語』のような、女性同士の親密さをテンプレ的な舞台のみで描くだけでは飽き足らず、さらにこのテーマを第二の戦略でエッセイにまとめた。吉屋は『花物語』を少女雑誌に発表していた同じ時期に、エリカ・フリードマンが 「我々が『百合』と考えるものの多くの原型」と呼ぶ『屋根裏の二処女』を発表している*13。
この作品にも若い女性同士の関係が描かれているが、『屋根裏の二処女』には『花物語』と大きく異なる点がある。第一に、これは短編集ではなく、小説(吉屋の処女作)であることだ。どうやら吉屋は商業的な目的ではなく、むしろ個人的な作品として、少女雑誌では書きたかったけれど書けなかったようなテーマや話題を提供するためにこれを執筆したようだ。多くの処女作がそうであるように、この作品も、高校卒業後、自身が師範学校に通っていた頃のことを書いた半自伝的なものである。
この小説の最も重要な舞台(タイトルにある『屋根裏』)は、女学校ではなく、「女子青年会」が運営する女子寮であり、これは日本キリスト教女子青年会(Young Women’s Christian Association; YWCA)のことをやや婉曲的に示したものである*14。もともと日本YWCAは、多くの海外キリスト教宣教活動の一要素として1905年に設立されたが、伝道活動にはあまり重点を置かず、中産階級の女性、特に中等教育を受けている女性への働きかけに重点を置いていた。東京YWCA の主要な活動の一つは、学校に通うために上京してくる若い女性たちを住まわすためのホステルの設立であり、最初の二つのホステルは1908年に開設され、キリスト教徒および非キリスト教徒両方の入居が許可されていた*15。
吉屋は、保育士になるための勉強をしていたときにこのホステルの一つ (あるいはその後建てられた別の一つ)に滞在し、これが、『屋根裏の二処女』の寮のモデルになったのだ。また、YWCAの「C(Christian;キリスト教)」を外し、主人公の二人(章子と秋津(※訳注:作中では「秋津さん」呼びが多いが、実際の名前は秋津環であるため、翻訳文中では章子と環と表記する))にキリスト教を否定させることで、吉屋はキリスト教的な設定からさらに距離を置くことにした。これに関し、ミチコ・スズキは、『屋根裏の二処女』では、同性同士の恋愛がこの宗教と真っ向から対立する設定になっている、と指摘した:「章子は、真の自分自身を認めるために、キリスト教の教えと、寮内におけるその実践とを乗り越える必要がある」*16。もしそうならば、これは、シモンズやカーペンターがキリスト教の同性愛禁止を回避し、代替道徳の観点からその実践を正当化しようとしたことを彷彿とさせる*17。
また、『屋根裏の二処女』のペアは、カーペンターが年下の少年と年上の少年または男性との関係を奨励するために書いたものや、本作における吉屋自身の色艶をも彷彿とさせるものでもある。現実の吉屋は、YWCAの寮に入り、菊池ゆきえと交際を始めたときには、既に成人していた。しかし、『屋根裏の二処女』の登場人物であり、自分をモデルにした章子は、菊池をモデルにした環に比べると年齢が不詳で、比較的子供っぽく描かれている:「いつも涙を流し、メランコリックで、過去を懐かしむ、未熟なキャラクター……(章子)は、年上の恋人を遠くから慕う年下の女の子の典型的な姿である」*18。
以前の物語と比較できるのは、ここまでである:『花物語』の登場人物とは異なり、章子と環は物語が終わりを迎えても関係を続けており、少なくともその後の人生を共に歩んでいったという可能性があるのだ*19。吉屋自身は菊池と別れたが、数年後に門馬千代と出会うことで人生の伴侶を得ている。
吉屋と門馬の共同生活は、ある意味で『屋根裏の二処女』や『花物語』に見られるのと同じ年齢差関係で特徴づけられていたといえる:吉屋は門馬より三歳年上で、門馬は吉屋を「お姉さん」と呼んで手紙のやり取りをしていた。また、吉屋は門馬を養女として迎え、法律上の娘とすることで両者の関係を公的なものにしたことは有名な話である。しかし、このことは、二人がお互いを対等な恋愛パートナーとして意識していなかったことを意味するものではない:二人は互いに結婚を望んでおり、吉屋は、戦後、日本の法律が改正されて二人が結婚できる可能性がないことが明らかになった後、養子という方式を採用したようである*20。
門馬と出会ってから、吉屋は1925年1月から8月まで独自出版していた雑誌『黒薔薇(くろしょうび)』にて、同性間の恋愛をテーマにした最後の執筆活動を行った。特に、『或る愚かしき者の話』は、『屋根裏の二処女』の暗部ともいうべき内容で、二人の女性の関係が、一方の女性が男に凄惨なやり方で殺されるという結末を迎えるが、これは、彼女が相手を裏切って普通の結婚を追い求めた結果であることが仄めかされている*21。
翌年、吉屋と門馬は共に家庭を築いた。吉屋は「1920年代後半から30年代にかけての政治的、社会的な状況の変化の中で、(少女小説以外の)文学的ニッチを確立し、堅実で幅広い読者を確保するために」女性誌に執筆するようになる。彼女の新しい戦略は、少女や女性同士の恋愛関係という考えを強調せず、「大人の同性同士の恋愛を、異性愛に代わるものとしてではなく、一種の姉妹愛として、異性愛を補完する女性のアイデンティティーの不可欠な一部分として(表現する)」ことに重きを置いたものであった。これによって、彼女の登場人物たちは、典型的なエス主人公の運命を避け、代わりに 『女性の同性愛…(中略)…結婚や母性という経験を経たとしても(あるいはそれゆえに)耐え忍び持続化していく、激しい友情』を経験することができるようになったのだ*22。
吉屋は晩年を門馬とともに、鎌倉で生活した―『青い花』の主要な舞台となる沿岸部の都市である。志村貴子は漫画のあとがきで、編集者とともに、作中に登場する様々な建物のモデルとなる写真を入手するために鎌倉を訪れたときのことを述べている。現在は博物館となっている吉屋邸を訪れようとするが、残念ながら休館日だったようだ(『青い花』(1) p. 190/SBF, 1:190)。
吉屋信子は1973年7月11日、門馬千代に見守られながらこの世を去った―偶然にも、それは志村貴子が生まれるわずか三カ月前のことであった。吉屋が半世紀以上にわたって開拓してきたエス文学は、その頃までに、次章で述べるような新しいタイプの少女文学に引き継がれていたのである。
###############
今回は吉屋信子さんについての章でしたが、僕は吉屋さんのこと、作品に触れたことがないを通り越して、ご本人の存在すらほぼ知らないレベルでした(もちろん青い花のあとがきで触れられていたこともあり、目にしたことはあったはずですが…)。
吉屋さんは、Wikipediaにも記事が(明治の方にしては珍しく)写真付きで存在しましたね。
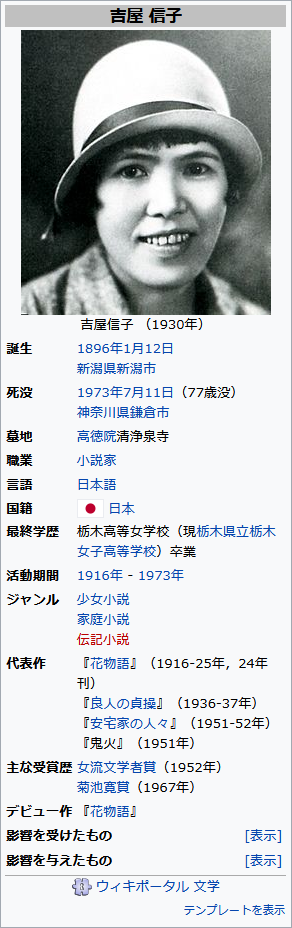
うーん、署長の娘さんという感じの、精悍で凛々しく、大変利発そうな相好をしてらっしゃる…!
俄然、著作の方にも興味が湧いてきましたね!
(…って、普通に記事を読んでて興味が湧いただけで、見た目どうこうは全く関係ないですし、今の時代あんまり良くないジョークでしょうか。)
我らが青空文庫で、サクッと作品の方にお目にかかることは出来ないかなと思い検索してみましたが……
www.aozora.gr.jp
残念ながら吉屋さんの作品はまだ存在しませんね。
そもそも吉屋さんが亡くなられたのは、記事最後にもありましたが1973年のことで、著作権の消滅って30年ぐらいじゃなかったっけ?…と思い調べ直したら、Wikipediaによると原則として著作者の死後50年、しかし2018年のTPP11法改正により、70年に延長されたそうで、50年の時点でもまだなのに、さらに20年先になり、吉屋作品の著作権が切れるのは2043年ということで、青空文庫での公開がまだまだ先なのは当たり前でしたか…!
間違いなく『青い花』ひいては志村さんご自身に大いなる影響を与えたと思われる傑作群、きちんと書店を介して手に取って蔵書に入れておくのがベストという話かもしれませんね。
いやぁ~それにしても、本題の考察記事、相変わらず難解っすね…!
果たして志村さんが、カーペンターやシモンズに端を発する社会学を意識し、そこに何らかのメッセージを込めて世間に物申す形で物語を描かれているのではないかという部分については、個人的には甚だ疑問符がついてしまう所かもしれませんが(笑)、結局青い花そして志村作品には、僕のような浅い読者でも心の底から楽しめるエンタメ性と、Frankさんのような考察ガチ勢の方をも満足させる奥深さとが、絶妙なバランスかつ極めて高いレベルで共存している最高の漫画作品であることは疑いようがない……その一言に尽きると思います。
僕は、社会的な側面よりむしろ、志村さんの作品は人間の心や気持ちの表現、内面・心情描写の秀逸さがマジで図抜けていると思うクチですけど、総合して「リアルさが神懸かっている、歴史に残る作品・作家さん」と評するに値してやまないという感じですね。
まぁ、もし志村さんご本人が目にされたら「買い被りすぎ(笑)」というか「そんなプレッシャーかかるような言葉、やめちくりぃ~」と思われるだけかもしれませんが(別に思われないかもしれず、純粋に嬉しい言葉と受け止めていただけたら幸甚の至りに存じますが…)、こんな非常に細かくマニアックな考察記事にまで目を通される方はほぼ間違いなく同意見をもたれている方に違いないですし、これは本当にファンの総意なのです、みんな大好き志村さん…!…と勝手に全体の意見を決め付けて(笑)、今回はおしまいとさせていただきましょう。
*1:Jennifer Robertson, “Yoshiya Nobuko: Out and Outspoken in Practice and Prose,” in Same‐Sex Cultures and Sexualities: An Anthropological Reader, ed. Jennifer Robertson (Malden, MA: Blackwell, 2005), 196–97, https://doi.org/10.1002/9780470775981.ch11
*2:Hiromi Tsuchiya Dollase, “Yoshiya Nobuko’s ‘Yaneura no nishojo’: In Search of Literary Possibilities in ‘Shōjo’ Narratives,” English supplement, U.S.-Japan Women’s Journal, no. 20/21 (2001), 153, https://www.jstor.org/stable/42772176
*3:Pflugfelder, “‘S’ is for Sister,” 153–55.
*4:Nobuko Yoshiya, Yellow Rose, trans. Sarah Frederick, 2nd ed. (Los Angeles: Expanded Editions, 2016), chap. 4, Kindle
*5:Michiko Suzuki, “The Translation of Edward Carpenter’s Intermediate Sex in Early Twentieth-Century Japan,” in Sexology and Translation: Cultural and Scientific Encounters Across the Modern World, ed. Heike Bauer (Philadelphia: Temple University Press, 2015), 205–9.
*6:Shane Butler, “A Problem in Greek Ethics, 1867–2019: A History,” John Addington Symonds Project, accessed February 13, 2022, https://symondsproject.org/greek-ethics-history
*7:John Addington Symonds, A Problem in Greek Ethics, being an Inquiry into the Phenomenon of Sexual Inversion, addressed especially to medical psychologists and jurists (London: privately-pub., 1901), 8, 13, https://archive.org/details/cu31924021844950
*8:Symonds to Carpenter, 29 January 1893, in Letters of John Addington Symonds, ed. Herbert M. Schueller and Robert L. Peters, vol. 3, 1885–1893 (Detroit MI:Wayne State University Press, 1969), 810–811, https://archive.org/details/lettersofjohnadd0003symo
*9:Josephine Crawley Quinn and Christopher Brooke, “‘Affection in Education’: Edward Carpenter, John Addington Symonds, and the Politics of Greek Love,” in Ideas of Education: Philosophy and Politics from Plato to Dewey, ed. Christopher Brooke and Elizabeth Frazer (London: Routledge, 2013), 255.
*10:Edward Carpenter, “Affection in Education,” in The Intermediate Sex: A Study of Some Transitional Types of Men and Women (London: Swan Sonnenschein, 1908), 103, https://archive.org/details/B20442178
*11:Carpenter, “Affection in Education,” 105. シモンズは、レズビアニズムという話題にはさらに厳しかった:初期のサッフォーの例に首を向けた後、「後期ギリシア人は、それを容認しながらも、名誉で社会的に有用な感情としてではなく、むしろ自然の奇異や悪徳とみなしていた。…(中略)…その結果、ギリシア人は少年愛を利用し、高貴なものにしたが、レズビアンの愛は現代で追求するのと同じ退廃の道を歩むことになった」と主張した。Symonds, A Problem in Greek Ethics, 71.
*12:Suzuki, “The Translation of Edward Carpenter’s Intermediate Sex,” 206–8.
*13:Erica Friedman, review of Yaneura no nishojo, by Nobuko Yoshiya, Okazu (blog), May 10, 2010, https://okazu.yuricon.com/2010/05/09/yuri-novel-yaneura-no-nishojo. Nobuko Yoshiya, Yaneura no nishojo (Tokyo: Kokusho Kankōkai, 2003). 花物語同様、屋根裏の二処女は一度も公式な英語翻訳がなされていない。
*14:Suzuki, Becoming Modern Women, 43.
*15:Margaret Prang, A Heart at Leisure from Itself: Caroline Macdonald of Japan (Vancouver: UBC Press, 1995), 41–42, 61.
*16:Suzuki, Becoming Modern Women, 46.
*17:この点で特筆すべきは、同時代の一部の人々と異なり、シモンズとカーペンターの二人は、精神的な関係だけでなく身体的な関係も含むものとして同性愛を捉えていたことが挙げられよう。Quinn and Brooke, “‘Affection in Education’: Edward Carpenter,” 259–60.
*18:Suzuki, Becoming Modern Women, 44–45.
*19:改めて、この点でも、シモンズや特にカーペンターは同じように「男性の愛を『揺るぎない献身と生涯続くつながり』として示そうとした」のであり、そのような関係が、エスの関係と同様に本質的に期限付きであるとしていたギリシャのモデルとは対照的であったといえる。Quinn and Brooke, “‘Affection in Education’: Edward Carpenter,” 260.
*20:Robertson, “Yoshiya Nobuko: Out and Outspoken,” 201–3.
*21:Suzuki, Becoming Modern Women, 54–59.
*22:Suzuki, Becoming Modern Women, 60. 太字強調は原文より。
